10月8日、京都大学の北川進特別教授がノーベル化学賞を受賞した。テレビの速報を見た瞬間、胸の奥が静かにざわめいた。
「固体の中に“空間”を設計する」。その言葉はあまりに静かで、しかし確かに、世界の見え方を変える響きを持っていた。
報道の多くは「多孔性金属錯体=MOFの開発」と淡々と伝えた。けれど僕は、その科学の奥にある“孤独と想像力”の物語を感じた。
MOFとは何か──「固体に空間をデザインする」という思想
北川進が挑んだのは、「固体=詰まっているもの」という常識の破壊だった。MOF(金属有機構造体)は、金属イオンと有機分子をブロックのように組み合わせ、分子スケールの空洞を持たせた素材。
その発想は、技術というより哲学に近い。「なぜ物質は空っぽではいけないのか?」。そんな問いを、彼は化学の言葉で描いた。
ノーベル委員会はこう述べている。
「物質に“空間”をデザインする発想が、化学を建築の領域へと引き上げた」(CNN Japan)。
科学とは、世界の“余白”を探す行為だ。
情報が詰まりすぎた現代社会。僕たちが無意識に求めているのも、もしかしたら“空間”という名の余白なのかもしれない。
1997年、「気体を吸う固体」が生まれた日
1997年、京都大学の一室で、北川進のチームが「気体を吸う固体」を実証した。その瞬間、化学の地図は書き換えられた。
CO₂や水素、メタンといった分子が、設計された孔の中に吸着される。人の手で“分子の部屋”をつくるという発想は、世界の研究者たちを驚かせた。
(出典:Science Portal)
北川は言う。「これは技術ではなく、概念だ」。MOFとは、物質そのものではなく、“世界の見方”を変える思想のようなものだった。
静かな語り、熱い構造──北川進という研究者
彼の講演を聞いたことがある。静かな声、少ない身振り。けれどその言葉の一つひとつが、実験室の空気を震わせるように熱を帯びていた。
「化学とは、“空間をデザインする”学問です」。その信念に迷いはない。学生たちは分子構造を“建築模型”のように描き、「美しい構造をつくれ」と言葉を受け取る。
京都大学iCeMSの理念「物質と生命の融合」。北川進はその思想を、言葉ではなく“構造”で証明してきた。
科学は、孤独を抱えてでも見たい“風景”がある。
その孤独を、彼は恐れなかったのだと思う。
ノーベル賞が示したもの──概念が社会を動かす
ノーベル賞は発見の早さではなく、“時間がその価値を証明したもの”に贈られる。MOFが評価されたのは、単なる素材開発ではなく、社会に届く科学だったからだ。
CO₂分離、水素社会、触媒設計。北川が描いた分子の建築は、今まさに地球規模の課題と接続している。
(参考:Chem-Station)
AIや量子技術が進化しても、“空間の意味”を問い直すのは人間の仕事だ。今回の受賞は、科学がまだ人の想像力の領域にあることを静かに告げている。
応用の先にある“詩”──MOFが連れ戻した感性
MOFは今、環境・エネルギー・医療などあらゆる分野で応用され始めている。
- CO₂吸着・再利用技術(CCUS)
- 水素やメタンの貯蔵素材
- ドラッグデリバリーや電子材料
だが、僕が心を打たれるのは“応用”ではない。
科学に再び“詩”を取り戻した点だ。
北川進は、数字よりも「美しい構造」を信じた。そしてその美しさが、地球の未来を包みこむ力を持っていた。
科学とは、精密さの中に宿る詩のこと。MOFは、その詩を物質で書いた一篇だ。
ニュースを超えて──想像力という名の物質
人が見えないものに手を伸ばすとき、そこに未来が生まれる。北川進が追い続けた“空間”は、希望という名のもうひとつの物質だったのかもしれない。
ニュースの文脈を超えて思う。
これは「科学の勝利」ではなく、「人間の想像力の証明」なのだ。
科学がまだ、人の手の中にあるという祈り。

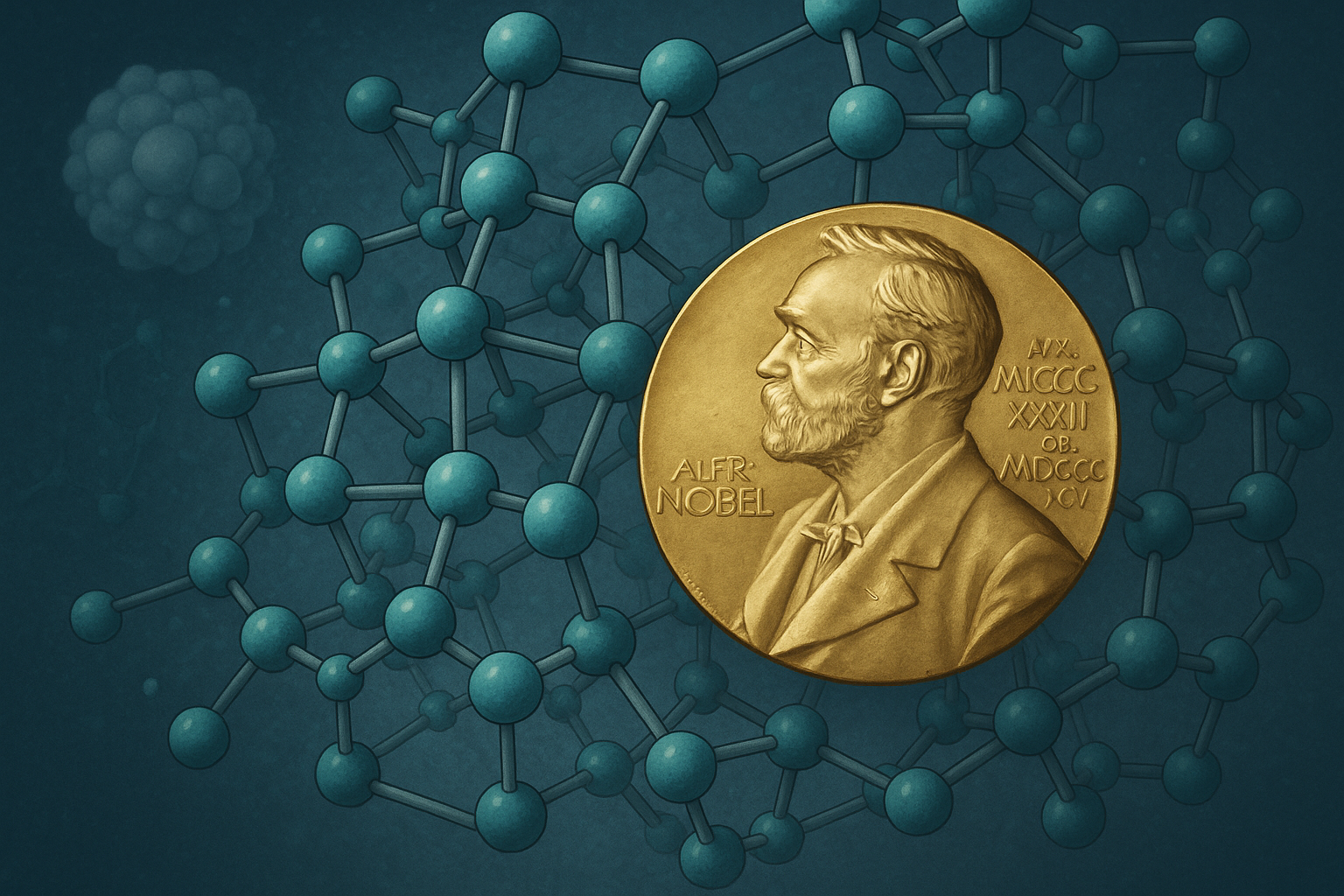

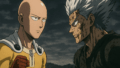
コメント